

(S-O-R)理論
同じ環境で
同じ情報が与えられても
どう感じ
どう行動するかには
個人差があります。
事実は1つでも
解釈は人それぞれに違うからです。
これを心理学で
(S-O-R)理論といいます。
※ S:Stimulus(刺激)、O:Organism(生活体)、R:Response(反応)
※ 心理学でいうところのOrganismは人、人の認知、人の感覚・意識・感情・感性
同じS(刺激)を与えても
O(その人がどう感じ、考えるか)によって
R(反応)は変わる
という考え方です。
同じ会社で
同じ商品を扱う
同じ仕事をしているのに
会社に自信を持ち
商品に自信を持ち
職業に自信を持ち
そんな自分に自信を持ち
仕事をしている人と
自分に自信がなく
会社に不満を持ち
商品に不満を持ち
職業に自信がなく
仕事をしている人とでは
当然
日々の使う言葉
行動の質
行動の量が
変わってきます。
使う言葉
行動の質と量が変われば
成果も当然変わってきます。
行動パターンの差の要因となっている
O(人の認知、感覚、意識、感情)の違いは
何から生まれるのしょうか。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

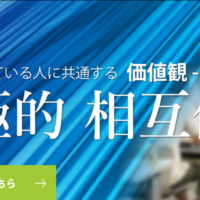
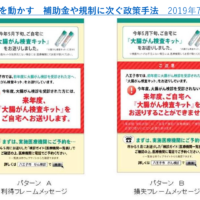
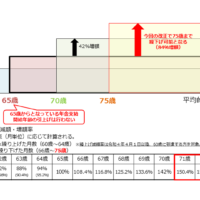

この記事へのコメントはありません。